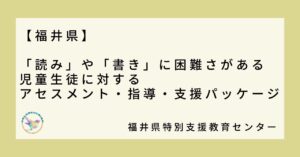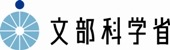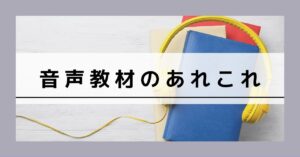文部科学省の事業、令和5年度【音声教材普及推進会議】の中で、東京大学先端科学技術研究センター近藤武夫先生によって行われた講演の動画です。
会議の中では、文部科学省の行政説明、座談会、音声教材を開発・研究、提供されている団体の発表も行われました。年に一度開催され、教育委員会や支援学校、支援級、通級の先生方が全国各地から参加されています。コロナ禍以降、保護者の会場への参加はできなくなっていますが、文部科学省の公式YouTubeチャンネルに各動画が公開されており、自由に聴講することができます。
10月に入ってディスレクシア月間がはじまり、また、近藤先生の講演で時代的背景の振り返りやさまざまな配慮事例などを拝聴していく中で、子どもたちのニーズに向き合って、ICTの活用がGIGAスクール構想によって教育現場に普及してきた現在に至るまでに、音声教材や拡大教科書の普及をはじめ、読み書きの支援にこれまで携わってきた皆さんの並々ならぬご尽力のおかげで今がある事を噛みしめています。
近藤先生の講演も、文科省や各団体発表も、とてもていねいにわかりやすくご説明いただいているので、アセスメントツールや音声教材について理解を深めることができました。
『担任を一人にしない』
『学校を孤独にしない』
『教師ひとりに押し付けない。地域で支えていく』
これは読み書き支援に関わらずですが、学校への地域での後方支援が重要なことについての説明されていた部分にも、とても共感しました。
『親と子を孤独にしない』『誰一人取り残さない』にもつながっていくと思います。
不安や懸念がどうにも払拭されないことによってSTOPがかけられ、先生と親子、双方で苦しい思いをして疲弊していたり、子どものニーズに合う支援が開始されず、無気力の状態が引き起こされて学習の空白期間ができていくということは、現在でも全国でしばしば起きています。
京都府の支援体制や後方支援の実践例は、保護者としても大変心強いです。
特別支援学校のセンター的機能について、まだまだ知らない方も多いと思います。私も、知ったのは今年に入ってからでした。もっと早く、うちの子がまだ小学生だったあの時に知っていたら・・・!と、悔しい思いが残っています。
近藤先生もおっしゃっていましたが、仕組みとしては全国にあるにはあるけれど広まっていきにくさがあり、同時に、『支援者さんも一人にしない』ことも重要なのだと思います。
公平な学習機会の保障のためには、社会的な障壁の除去(合理的配慮)が必要です。
どうか、京都府のような支援体制と、音声教材の自由な利用、子どもたちのニーズに合った支援策、そのためのアセスメントの実施が一日も早く全国へ浸透してほしいです。
(F)
資料の掲載ページは、【令和5年度 音声教材普及推進会議】と検索すると、出てきます。
(文部科学省教科書課による行政説明や、各団体発表の資料や動画も一緒に掲載されています。)
動画内で紹介されていたアセスメントツール
1.標準化されたアセスメント
URAWSSⅡウラウス ツー、STRAW-Rストロウ アール、稲垣ガイドライン、日本版KABCⅡケイエービーシー ツー
2.支援への反応から評価
RTI(Response to instruction介入や支援に対する反応)モデルに基づく評価方法
”※どちらかではなく必要に応じて両者を活用”
動画内で紹介されていたWebサイト
・東大先端研(東京大学先端科学技術研究センター 社会包摂システム分野)
近藤武夫先生の研究室。子どもたちの成長段階(小学生~大学生・就労)に応じた、さまざまな障害に関する支援を行っています。
・独立行政法人 大学入試センター 令和6年度受験上の配慮案内
動画内で紹介されていた参考文献
アセスメント
・河野俊寛、平林ルミ(2016)能力評価とアセスメント。
・近藤武夫編著 学校でのICT利用による読み書き支援─合理的配慮のための具体的な実践。金子書房 P18-25
学校の体制整備
・AccessReading アクセスリーディング(2018)
音声教材配信手引き(通常学級担任、通級指導学級担任、教育委員会向け)
動画内での近藤先生のコメント
『子どもたちに音声教材が届くまでの、それぞれの立場ごとの関り方についてなどが掲載されています。』
・京都府総合教育センター
ICTを活用した個に応じた指導法の研究
動画内での近藤先生のコメント
『音声教材の活用や、単元テストの中で読み上げ等を用いて実施し、評価をしている事例などもたくさん掲載されています。』
・福井県特別支援教育センター
「読み」や「書き」に困難さがある児童生徒に対するアセスメント・指導・支援パッケージ
動画内での近藤先生のコメント
『教育段階ごとに非常に詳しくまとめられている資料です』
入試の配慮
・近藤武夫(2017)高等学校や大学の入試の配慮や入学後の配慮.中等教育資料 66(9),104‐107.
・近藤武夫(2017)入試や試験での合理的配慮としてのICT利用 ─合理的配慮の合意形成に関する事例から─.LD,ADHD&ASD,15(3),20‐23
・近藤武夫(2017)障害者差別禁止を理解する.学校運営,668,6‐9.
・近藤武夫 編著(2016)学校でのICT利用による読み書き支援 合理的配慮のための具体的実践.金子書房
・近藤武夫(2016)障害のある受験生に対する合理的配慮.大学時報,65(370)44‐49
・近藤武夫(2016)入学者選抜試験における受験上の配慮:配慮を受けるまでの実際について.中等教育資料,65,88‐91.
音声教材普及推進会議に参加されていた団体
・公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会(マルチメディアデイジー教科書)
・東京大学先端科学技術研究センター(AccessReading)
・特定非営利活動法人エッジ(音声教材BEAM)
音声教材BEAMに関するLINE相談も開始。詳しくは、発表動画の中やHPでご確認ください。
・茨城大学(ペンでタッチすると読める音声付教科書)
・広島大学(UD‐BOOK(文字・画像付き音声教材))
・愛媛大学(UNLOCK)
利用者のニーズに合った音声教材を選ぶ際に参考になる、音声教材情報提供サイトもあります。カラフルバードの「音声教材あれこれ」の記事内でもご紹介しています。
近藤武夫先生が執筆された書籍
・『発達障害の子を育てる本 スマホ・タブレット活用編 健康ライブラリー』講談社
・『学校でのICT利用による読み書き支援: 合理的配慮のための具体的な実践 (ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育ナビ)』金子書房
・『タブレットPC・スマホ時代の子どもの教育 学習につまずきのある子どもたちの可能性を引き出し、未来の子どもを育てる』明治図書出版
・『学びに凸凹のある子が輝くデジタル時代の教育支援ガイド-子ども・保護者・教師からの100の提言 (ヒューマンケアブックス)』朝日新聞社