『読み書きに課題を感じたら~誰にどのように相談をすればよいのか』の記事では、ステップ1として、学校内の相談先の活用法をご紹介しました。ステップ2では、「検査などができる相談先」をご紹介していきます。
今回は⑨の「自治体の相談窓口(福祉課など)」についてです。検査はできませんが、受給者証の発行や様々な相談の総合窓口ですので、こちらでご紹介します。
児童発達支援や、放課後デイサービスを受ける際には受給者証が必要ですが、その窓口が市の福祉課になります。私は子供が年長の時に引っ越しをして療育を受けたかったので、その時最初に相談したのが福祉課でした。受給者証の手続きはもちろん、そこから発達支援センターを教えていただいたり、福祉の総合窓口といった感じです。
家族も含めて総合的に支援してくれます。私自身病気を持っており、子育ての大変さを訴えたところ市内で利用できる子育てサービス等も教えていただきました。主に受給者証の更新時(年1回)に面談を行い、今の家族の状況、サービスが合っているか等を確認していただいています。
また放課後等訪問支援を受ける際に、学校側に制度の趣旨を説明して下さったり、学校と療育先との間を取り持ってもらい、支援会議を開いていただいたりとお世話になっています。(福祉課の方が支援会議を開いてくださるのはまれのようです。)(E)
STEP2 病院や支援センターなど、検査を実施してもらえる場所を探す
①病院(小児神経科・児童精神科)
②発達支援センター
③教育相談(自治体立)
④教育相談(大学など)
⑤LD専門の相談施設(医療機関以外)
⑥言語聴覚士
⑦発達支援をする私設の支援室・学習教室など
⑧眼科・耳鼻科
⑨自治体の相談窓口(福祉課など)
カラフルバード~CBLD~

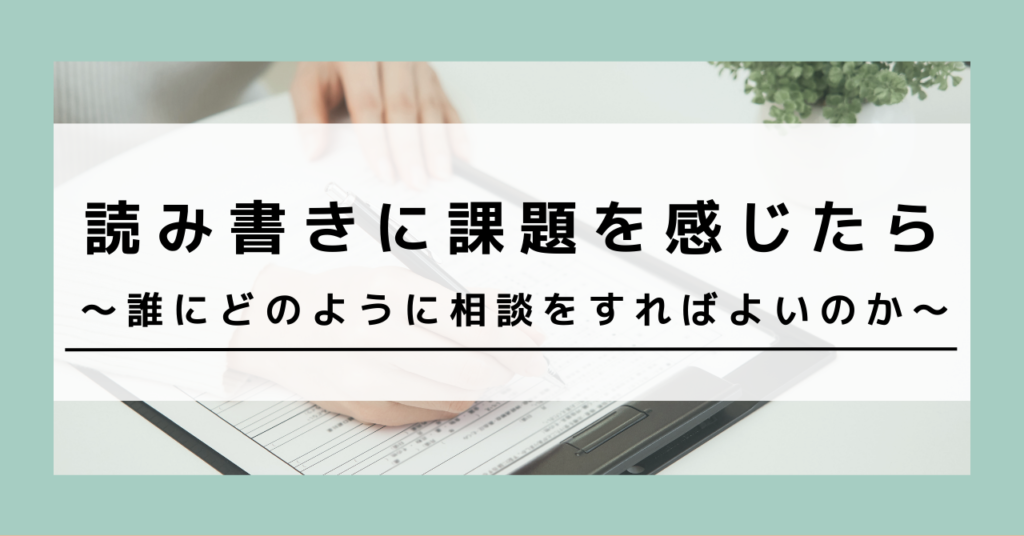
読み書きに課題を感じたら~誰にどのように相談をすればよいのか
宿題を嫌がる、時間がかかる、連絡帳を書いてこれていない。 読み書きの躓きに気づくきっかけは様々かと思いますが、それに気づいて支援につながるまでは想像以上に大変…