『LDっ子の受験報告』は、LDのある子ども達の受験体験談をご紹介するコーナーです。合理的配慮のコーナーで載せきれない、さまざまな方の受験までの道のりをご紹介していければと思っています。
今回は、2024年の中学受験における合理的配慮入試の報告です。
合理的配慮を実施しての中学入試は、CBLDデータバンクでご紹介しているこちらの#19-①の方と同じ学校を受験しています。
この方が最初の合理的配慮入試を2016年に行っていると聞いており、その後もこの学校では合理的配慮を入試で行っているものと思われたため、挑戦してみることにしました。
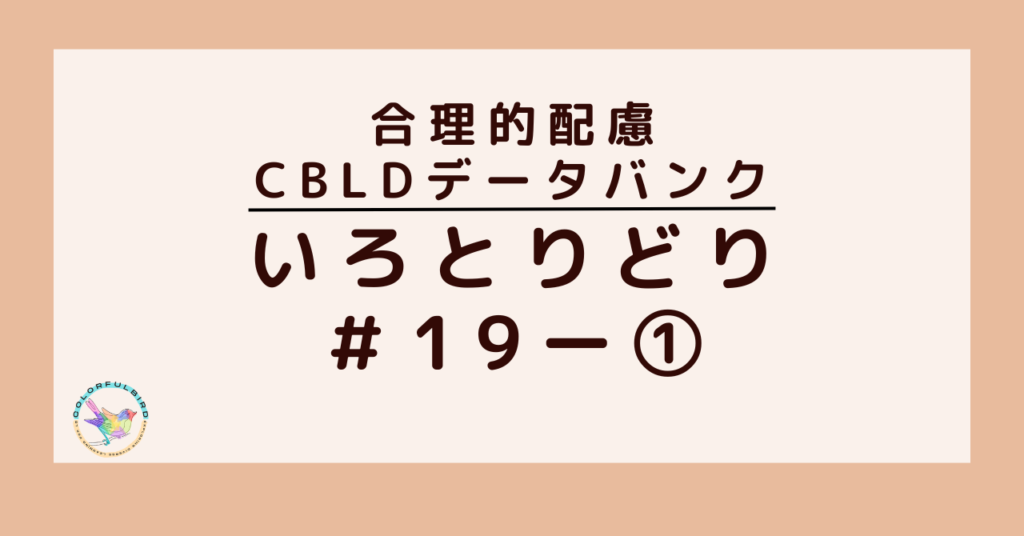
中学入試の合理的配慮
中学入試における合理的配慮を実施してもらうためには、やはり事前の準備をしっかりしておく必要があり、下手をすると年単位でスケジュールをしっかり意識しながら進めていく必要があります。
申請までの大まかな流れ
年によって、学校によって、必要な申請書類や情報は異なります。
しかし、大体の学校のこれまでの申請書類や手続きについての情報を集めたところ、『配慮実績』と『診断書』が必要になるであろうことは小4の段階で分かってきていたので、そのための準備を進めることにしました。
.
①配慮実績を6年生1学期までにある程度学校で実施しておいてもらう。
②受験のための診断書を書いてもらえる病院を探して受診しておく。
③診断書を作成するための検査を小5の秋冬に実施できるように、WISCなどは逆算して計画して取っておくかおかないかを見極める。
④受験校の学校見学や説明会は5年生のうちまでにまずは1度は行っておく。
配慮実績
読み書きに困難がありますが、うちの子の場合は、書字に特に課題があったため、GIGA端末のタブレットを利用してノートテイクを小4からしていました。
また、個別の配慮ではなかったのですが、学校自体が高学年からは作文はWordを使って作成することが基本だったため、「配慮」ではないにしても、「キーボード入力で作文を書く」、ということが行われている状態が実績として成立していました。
.
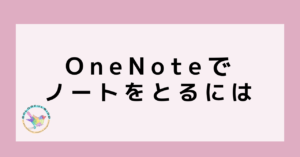
なお、申請書類を提出したあとには、受験校から小学校の方に、実態確認の電話がかかってきたようです。普段行っている状況を担任の先生から説明してもらったようです。
診断書
受験を検討し始めてから毎年各校の募集要項を読み比べていたのですが、診断書の扱いについては、学校により、年により結構違いました。
文科省は基本的には合理的配慮の実施に診断書は必ずしも必要ではない、としているため、診断書を不要としている年もありましたが、子の受験の年は、診断書が必要な年でした。
いずれにせよ、診断書を出してもらえるように準備をしていたほうが安心だと思います。
注意点としては、病院によっては初診から1年以上たたないと診断書を書いてくれないところもあります。
また、年によっては1年以内の検査結果を使うように指定のあるところもありました。申請時の1年以内で受検に影響の少ないタイミングというのが、小5の秋冬ということになるため、病院受診の際にその計画を早めに伝えていました。
なお、WISCは2年程度間をあけて受検した方がよいと言われるため、計画的に受検した方がいいでしょう。我が家は大学入試まで見据えてとるタイミングを計算しています。
診断書作成の際には、保護者と学校が作成する状況報告書も主治医に提出をして、その内容も踏まえて整合性のある内容で診断書を作成していただきました。
*子供の受験の前の年は、診断書が不要だったため、我が家は小5で検査を取り直したものはWISCだけでした。また、結果的に子供の受験の年は診断書の提出は必要でしたが、検査時期の指定はなかったため小6の時に子供の負担が増えることはありませんでした。
受験の年のスケジュール
公立高校の入試と違い、中学入試は学校同士のやりとりではなく、保護者と受験校が直接やりとりをすることになります。
また、この学校は12月末に推薦入試、2月に一般入試があるため、まずは推薦入試で配慮入試が行えるように動き、同時に一般入試の受験手続も行いました。
| ① 6月ごろ | 電話にて窓口へ問い合わせ。担当の方とその後はメールでやり取りを開始する。 |
| ② 9月初旬 | ・募集要項発表。配慮入試の相談スタート。診断書が必要かどうかなどが分かる。 ・保護者が状況報告書作成の上、学校記入欄の記載を小学校に依頼。 ・主治医に診断書作成を依頼(保護者作成の状況報告書も参考に主治医に提出) |
| ③ 10月中旬 | 推薦入試のための配慮入試申請書提出(状況報告書・診断書) |
| ④ 11月上旬 | 推薦入試の出願書類一式を提出(保護者作成の志願理由書と小学校作成の推薦書が大事) |
| ⑤ 11月下旬 | ・推薦入試一次書類審査選抜結果発表 ・一般入試のための配慮入試申請書提出(状況報告書・診断書)*推薦の時と全く同じもの |
| ⑥ 12月上旬 | 中学校に出向き、実施内容を打合せ。練習用のDVDを借りる。 |
| ⑦ 12月下旬 | 推薦入試実施→結果発表 |
| ⑧ 1月上旬 | 一般入試の出願書類一式を提出 |
| ⑨ 2月上旬 | 一般入試実施→結果発表 |
配慮内容・配慮方法
この学校は例年300~400字程度の作文がでるため、その作文部分をキーボードを使って解答することを希望しました。作文以外は普通の解答用紙に記入します。
中学校側から提示いただいた配慮方法は以下の通り
・PCは自前で持ってくること。ただし、デスクトップには消せないアプリ以外何も置かない。
・Wordファイルに解答。ただし、このWordは一文字ずつしか入力できないように設定されたもの。
・下書き欄からコピーをしてペーストをすることはできない。
・予測変換は利用可能。
・試験当日は学校のプリンタで印刷をするため、事前にプリンタのドライバーをインストールしておく。
・別室受験
・電源の持参
受験当日に、配慮入試についての回答書(許可書のようなもの)をいただきました。
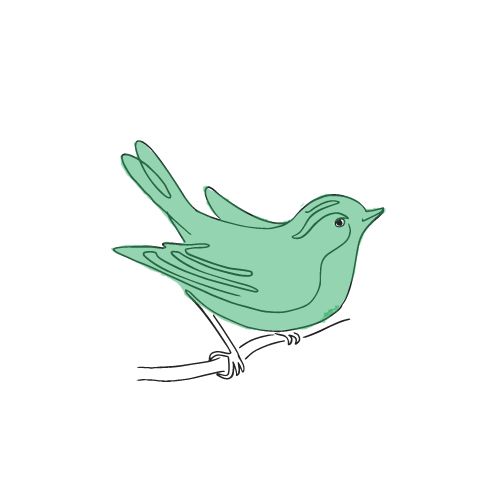
ちなみに、Wordが一文字ずつしか入力できず、子は解答するのをあきらめてしまいました…。
受験を終えて
推薦、一般とも不合格に終わりましたが、配慮入試を実施を経験することができ、この中学校にはとても感謝しています。キーボード入力の方法が大変煩わしく、子供本人が解答のモチベーションを失ってしまった点が残念でしたが、この経験は貴重なものでした。
不合格であったとしても、この入試で配慮をしていただいた実績は、今後の配慮を受ける際に活かされることになるかもしれません。
*ここの学校以外でもお友達でキーボード解答をしている学校もありました。そこも2月入試でしたが、秋から申請をしてやりとりをしているようでした。今後はこうしたPCを利用した配慮入試を行う学校も増えていくかもしれませんね。
(M)