学校の定期試験とは異なり、入試や検定試験は試験ごとにルールが異なります。毎年、大学共通テストでは、許可されていない道具を使用したことで失格になるケースが発生しています。学校では合理的配慮として認められていても、試験運営団体への確認不足が原因の一つと考えられます。学生は外部試験に慣れていないため、保護者(支援者)のサポートが重要になることがあります。今後、詳しい記事を数回にわたり掲載する予定です。
各種試験の基本原則として、公平かつ公正であることが求められます。障害の有無に関わらず、すべての受験者が自身の能力を十分に発揮できる環境を整えることが重要です。そのため、合理的配慮を申請する受験者と試験運営団体との間で合意を取る必要があります。
前回の記事はこちら
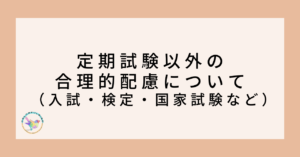
配慮を求める基本的な流れ
配慮のある試験を希望する際、問い合わせを行うと「どのような配慮を求めていますか」と質問されます。運営側が配慮方法を提案することはなく、配慮を必要とする人がその理由と具体的な配慮内容を説明する必要があります。
学校での実績と試行の重要性
試験によっては学校での実績が必要ではない場合もありますが、学校の定期試験でさまざまな配慮を試しておくことが望ましいです。一度も試したことがない方法で試験を受けると、本来の実力を発揮するのが難しいかもしれません。学校の試験等で実際に試してみて、自分が最も実力を発揮できる方法を確認し、その方法を申請することが重要です。
学校での配慮
学校での配慮は義務ですが、必要な配慮は当事者と相談しながら決めます。医師の意見書や検査結果をもとに、学校と話し合って合意する必要があります。ただし、配慮の実施には時間がかかる場合があります。困難に気づいたら、できるだけ早く学校に相談しましょう。
学校によっては、ICTを使った試験が認められることもありますが、まだ一般的ではありません。そのため、問題や解答用紙の拡大、リーディングトラッカー*やマーカーの使用、座席の位置などのアナログな配慮から始めるのも良いでしょう。2025年度から全国学力調査の中学理科がCBT*化されるため、今後はICT利用への理解が進むかもしれません。
*リーディングトラッカー(葉山町HP)

*CBT方式(ITパスポート試験HP)
学校の配慮実績の活用
学校の配慮実績を個別の教育支援計画・指導計画として作成することで、入学試験の配慮申請の資料として使用できます。公立私立問わず作成可能です。
実際の試験に向けての準備
受験したい試験がある場合、ホームページで詳細を確認しましょう。一般的な試験は年に1〜3回行われるため、時期によっては情報がないことがあります。まず実施時期を確認してください。ページにある受験要項などの資料を必ず確認してください。必要な持ち物や試験中に使用が許可されているものが記載されています。配慮のページで申請時期、申請方法、申請書類も確認してください。配慮の可否決定の時期も確認してください。
早めの準備
申請書類に医師の意見書や診断書が必要な場合、通院予約や書類作成の日数がかかるので準備が必要です。読み書きに関する配慮にはいくつかの書類が必要となるため、遅くとも受験する1〜2年前から計画を立てることをお勧めします。ただし高校受験の場合は中学入学直後から進めた方が良いでしょう。
公立高校入試における配慮申請
公立高校受験の配慮申請方法は自治体によって異なるため、通っている中学校との連携が重要です。実施実績がわかりにくいため、情報収集が必要です。都道府県の教育委員会のHPに高校入試に関する情報が掲載されているので、まずそちらで配慮についての情報を確認してください。ニュース*やXで流れた情報などで入試において実施された内容を定期的にチェックすることも有効かと思います。
*読み書きが難しい「ディスレクシア」とは?
高校入試で合理的配慮が行われた例も(解説マン)(YouTube石川テレビ公式チャンネル)
最後に
試験当日に配慮の申し出を行っても、大抵の場合は認められないことがほとんどです。非許可の道具を使用した場合、失格となる可能性もあります。試験に最良の状態で臨むために、十分な準備を行うことが重要です。
(にゃー)